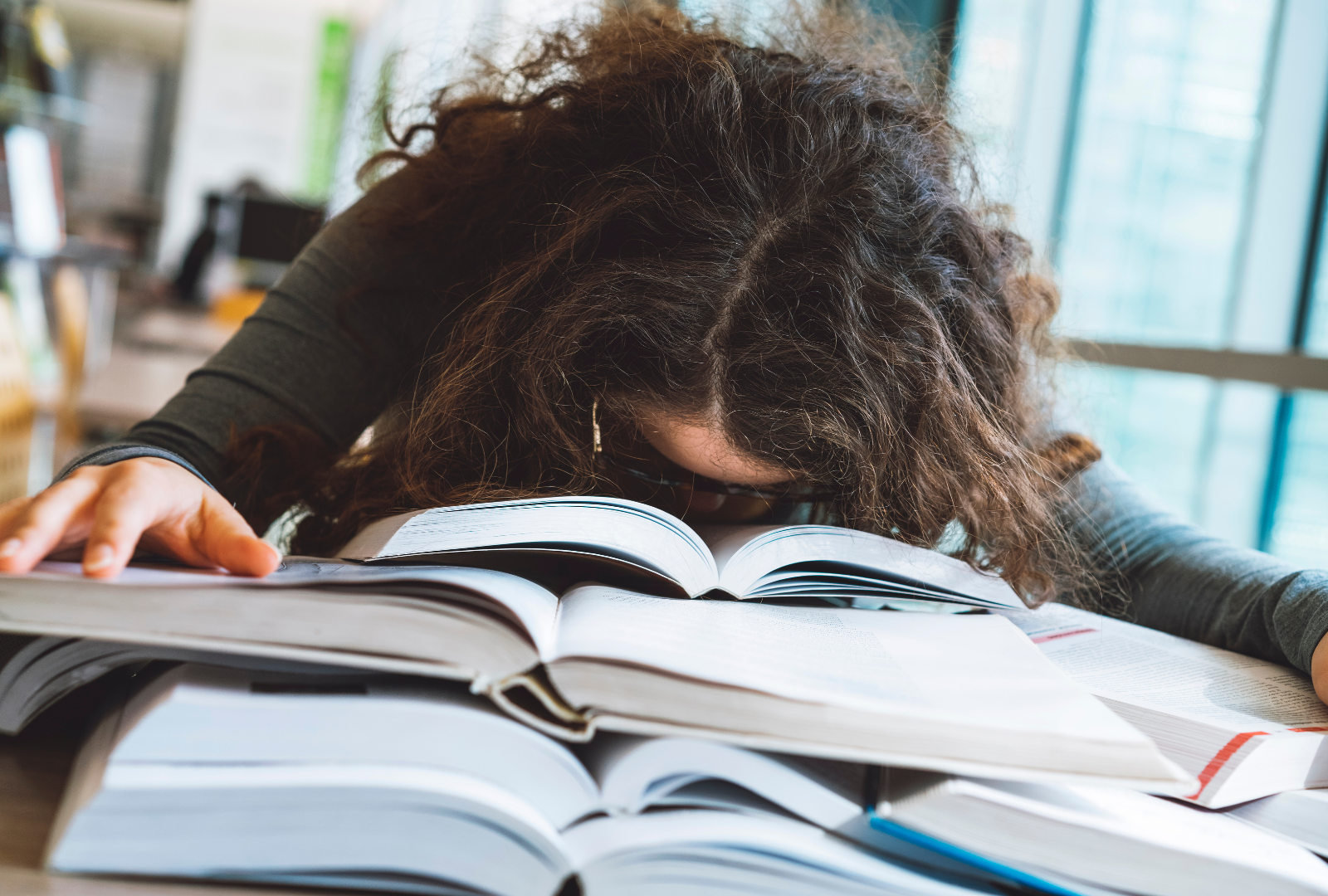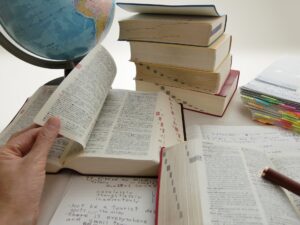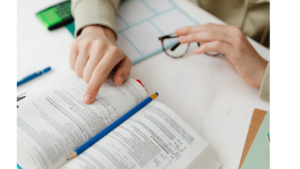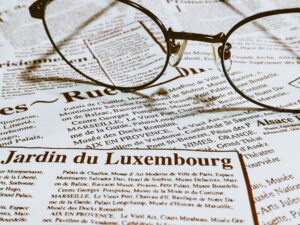― どれだけ頑張っても結果が出ない「7つの落とし穴」
身につかない学習法1:教科書と文法から入る
ほとんどの人が最初にやるのが「単語帳」と「文法書」。
けれど、これでは“脳の言語チャンネル”が開かない。
赤ちゃんは「主語」「動詞」「過去形」なんて知らずに話し始める。
音で世界を感じ、リズムで意味を掴んでいる。
つまり、“文字から”ではなく“音から”が、言語習得の自然な順序。
身につかない学習法2:非ネイティブ同士で会話練習をする
動画台本でも中村さんが語っていたように、
“音のリズムを身につけていない同士で会話練習する”のは逆効果。
関西弁を知らない人同士が「なんでやねん」と言い合っても、
リズムも心意気も伝わらないのと同じ。
音の文化を持たない状態でアウトプットしても、
“間違った音”が脳に固定されてしまう【43:0†動画台本【岡本さん共有】.pdf†L25-L37】。
身につかない学習法3:ネイティブと話せば上達すると思い込む
ネイティブと会話するのは良さそうに見えて、
実は「聴く力」が育っていない人には意味がない。
発音・抑揚・スピードに脳がついていかず、
ただ“英語を浴びた気”になって終わる。
本当の学びは「聴けるようになってから話す」。
順番を間違えると、脳の回路はつながらない【43:4†動画台本【岡本さん共有】.pdf†L16-L24】。
身につかない学習法4:シャドーイングで音をコピーしようとする
一見トレーニングっぽいが、
意味を理解せず音をなぞるだけのシャドーイングは、
“リズムの模倣”であって“言語の体得”ではない。
音を聴き、感情やニュアンスを“感じてから”声に出すこと。
それが“音を自分のものにする”ということだ。
身につかない学習法5:「ながら聴き」でインプットした気になる
最大の落とし穴。
ながら聴きは“音をBGM化”してしまい、脳の処理が浅くなる。
言語は「脳の聴覚野」を使って“意味を拾う”学問。
つまり、意識を100%“音”に向けないと回路が開かない。
耳は使っていても、脳が寝ている状態では、何も積み上がらない。
身につかない学習法6:留学すれば自然に話せると思っている
中村さん曰く、「留学は特効薬ではなく、運次第」。
授業で先生以外が非ネイティブなら、間違った発音が飛び交い、
正しい音のモデルが脳に入らない。
むしろ、ひとりでイヤホンをつけて“生の音声”を聴いていたほうが
よっぽど有意義だという【43:0†動画台本【岡本さん共有】.pdf†L35-L45】。
身につかない学習法7:「話すこと」ばかりに執着する
多くの人が「話さなきゃ忘れる」と焦るが、
聴く力が育っていないまま話しても“正確な音”は出てこない。
まずは“正しい音”を何度も聴いて脳に刻むこと。
「話す」は、自然に“溢れ出すもの”であって、“引き出すもの”ではない。
赤ちゃんが言葉を話すように、“耳から”が先だ。
まとめ:言葉は「覚えるもの」ではなく「染み込むもの」
語学が身につかない人の共通点は、
“勉強しよう”としてしまうこと。
でも、音の世界は努力ではなく感覚で掴むもの。
聴くことで脳の中に「音のチャンネル」ができ、
そこに単語や文法が“勝手に”貼りついていく。
つまり――
「まずは聴く」ことが、すべての始まり。